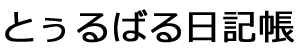430MHz帯用の5エレ八木アンテナ製作

ハムフェアで購入した430MHz用のアンテナ部品を使い5エレ八木アンテナの製作を行いました。その時購入した部品は、3Dプリンターで製作したエレメントとブームを固定する樹脂部品です。
1.購入品と構成部品
7部品の内訳分けは、エレメントとブーム固定用(エレメントホルダー)5点。他の部品は、ブームとポール相当品を固定する部品、ポールと三脚などを固定する部品として使用しました。


2.エレメント配置
いつものように見よう見まねなのでエレメントの長さ・配置は、JR2KHB局のページを参考にさせて頂きました。

3.加工・組立
1)給電部
SMAコネクターの方が良さそうでしたが手元にあるBNCで製作しました。そのため樹脂部品にそれ用の穴を開けています。

2)エレメントホルダーとブームの固定

白丸付近にφ6mmのアルミパイプが通る穴が空いていました。(黒色で穴が見ずらい。)
3)ポールとブーム固定

4)三脚に固定

1/4インチナット付プレートとポール下端固定用はM4ボルト・ナットで締結しました。
1/4インチナット付プレートのナットとポール下端固定用の干渉防止のためワッシャーで高さを調整しています。
4.調整・測定
給電部はBNCコネクター以降のラグ端子を含めた長さと思われ輻射器の長さを数ミリカットして共振周波数を合わせました。その後、八木アンテナに接続する同軸ケーブルは3.5DSFA 2mと3D2V 2mを使い簡易電界強度計で測定しました。SWRはIC-705のグラフから大体の値です。
| 周波数:433.02MHz | 無線機の出力(W) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アンテナ | 0.5 | 1 | 2.5 | 5 | SWR(無線機の値) |
| 5エレ八木 + 3.5DSFA 2m | 59 | 101 | 197 | 302 | 1.1 |
| 5エレ八木 + 3D2V 2m | 51 | 86 | 167 | 262 | 1.4 |
| カンテナ | 9 | 16 | 35 | 56 | 1.2 |
| RH770 | 12 | 22 | 50 | 85 | 1.2 |
| 5エレ八木 + 3.5DSFA 2m vs RH770比率(単位:%) | 492 | 459 | 394 | 355 | ー |
| 測定値の単位:mV | |||||
5.考察・感想
5エレ八木、3D2V 2mの同軸ケーブル、5W出力の組合せで測定された電圧を、3.5DSFA 2mの場合と比較数すると、無線機の出力4Wとほぼ同じになると思われます。同様に考えカンテナ、RH770と5エレ八木、3.5DSFA 2mを比較した場合、無線機の出力は1Wを下回ることになるので、多エレメントのアンテナは利得により出力が大きくななりすごいと感じました。(移動運用のアンテナはダイポールやRH770を使用しています。)
6.お試し運用
週末の天気がイマイチのため近所の高台で運用してみたが上記のようなメリットを感じる事は出来ませんでした。(ローカル局との交信のみで終了した。)う〜んなぜか?運用場所など色々あると思われます。

RH770・カンテナで運用した場所で行った方が比較しやすそうなので次回はロケーションを考慮して再度行う予定にします。